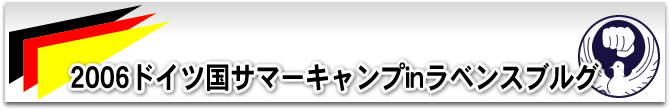和道会指定選手派遣・感想文

ドイツ遠征を終えて −空手を楽しんで練習する大切さ−
中京大学 二年 中村 悠子
今年の夏、和道会からの援助もあり、ドイツで行われる海外での空手の合宿に参加する事ができました。これも海外での遠征の機会を作って下さった和道会のおかげだと思っています。海外での組手のスタイルは日本とは違う物があり、今まで、目にした事のない空手の新しい扉を開いた気分でよい経験ができ、とても感謝しています。本当にありがとうございました。
私は去年の和道会のワールドカップで、初めての海外選手と試合をしましたが、海外でのスタイルは日本とは違い、フットワークも常にしていているし、突き技もあるけれど、蹴りのバリエーションがとても豊富だという事を感じました。
合宿では試合とは違い、一緒に向かい合って練習出来るので、海外の組手をすごく身近で感じる事ができとても楽しかったです。まず思ったのが、フットワークの違い!とても軽やかにフットワークをします。膝をうまく使って動き、その中に技のコンビネーションの中にフェイントを入れてきます。でもフットワークを高くしたりすると、リズムがとりやすいし、足が地面から浮く時があるので、その瞬間を狙うと動きが止まるから、いいとアドバイスを受けました。そして、日本と違うのは、蹴りの使い方です。前回経験した試合で手の長さを生かした伸びる突きで攻撃してくるし、どこかわからない所から蹴り技が出てきます。
海外の練習では、蹴りの1本で終わる技のパターン練習が全くないのです!1本で終わらず、フェイントを入れたりします。左足での中段・上段といった普段、技の組み合わせではなく、顔の左側を蹴ったと思ったら、すかさず裏回し蹴りだったり、足をつくと見せかけてのこかしといった技はやっぱり日本人の目には慣れていないので、練習中でも何度も読めない蹴りが顔をかすりました。海外独特のフットワークを左右や前後にふるのと同時に蹴り足を抱え込むのですが、抱え込む足が上段や中段とわかれておらず、前蹴りの時のように膝を高く抱え込む事によって、一定の場所から出てくるので、本当にどこにくるのかわからない蹴りになるのが海外選手の蹴りの特徴だと思いました。
私は試合で蹴りを出すタイプなので、蹴り技のコンビネーションの練習はとても楽しかったです。もっと蹴りのバリエーションを増やす為にも海外選手のように日頃の練習の回数から今より数やパターンを増やして、蹴りの練習をしていきたいです。それと、海外選手の特徴はサウスポーにも強いという事。私はサウスポの人が相手だと動きが普段通りに動かず止まってしまします。それはいつもやり慣れていないからだと思いますが、海外での練習は左構えが終わったら足をチェンジして両構えからの技を練習します。海外選手はやりやすい方の構えはあると思うけれど、きっと苦手構えがないと思います。普段から両方やっていれば、相手のやりにくい方に構えたりできたり、ふとした瞬間でも技が出るので、両方の構えから技が出るのは本当に理想だと思いました。
日本ではよく、1本で終わらず2・3本つけ!と言われますが、海外では違います。3本は当たり前、日本以上の5・6本と連続で技を出しています。試合中1本目で決まればいいですが、これだけの連続技を日頃からやっているので試合中でも反射的に出てるんだと思います。松久先輩の試合を見ていて思ったのが、普通の突きとスライドの突きのスピードの違いです。普段とは違い体制を変えないで足を踏み込まず膝を落とすことによってモーションが減り、体重が前にのり勢いがそのまま拳にのっていくので、遠くから突けるし、威力もあるので、すごい上段突きだなと思いました。理屈はわかっていても簡単に出来るものではありません。見ているだけでなく、私もこの上段突きを見につけて自分の技にできたら試合の流れを変えれると思います。スピードがある突きや技を作っていくには土台やベースがしっかりしていないとダメなので、バランスを保ったり、それなりの筋肉が必要だと感じたので、筋トレも時期を調整してやっていきたいと思います。
技術面ではないのですが、日本は合宿やセミナーになると、子供の参加者は多いのですが、ドイツでは1000人を超える参加者が集まる中、空手競技の年齢層の幅が広いというのが驚きでした。20代を越える人はもちろん、60代を超える人、おじいちゃん、おばあちゃんまでもが若い子供達のパワーに負けまいと、一緒に練習し汗を流していました。空手は世代を超えてできるスポーツだという事を感じれたのは印象的でした。
今回のドイツ遠征では技術面でも学ぶ事が多かったけれど気持ちの部分で自分の空手に対する気持ちを見つめ直す事が出来たと思います。ドイツの練習は、日本とは違う雰囲気でとても新鮮な練習ばかりだったので、いい緊張感を持って最後まで練習できました。お世話になった人への感謝の気持ちを含めてこの合宿を通して学んだ事を少しずつでもこれからの自分の組手や、練習に取り入れていき、レベルアップしていきたいです。